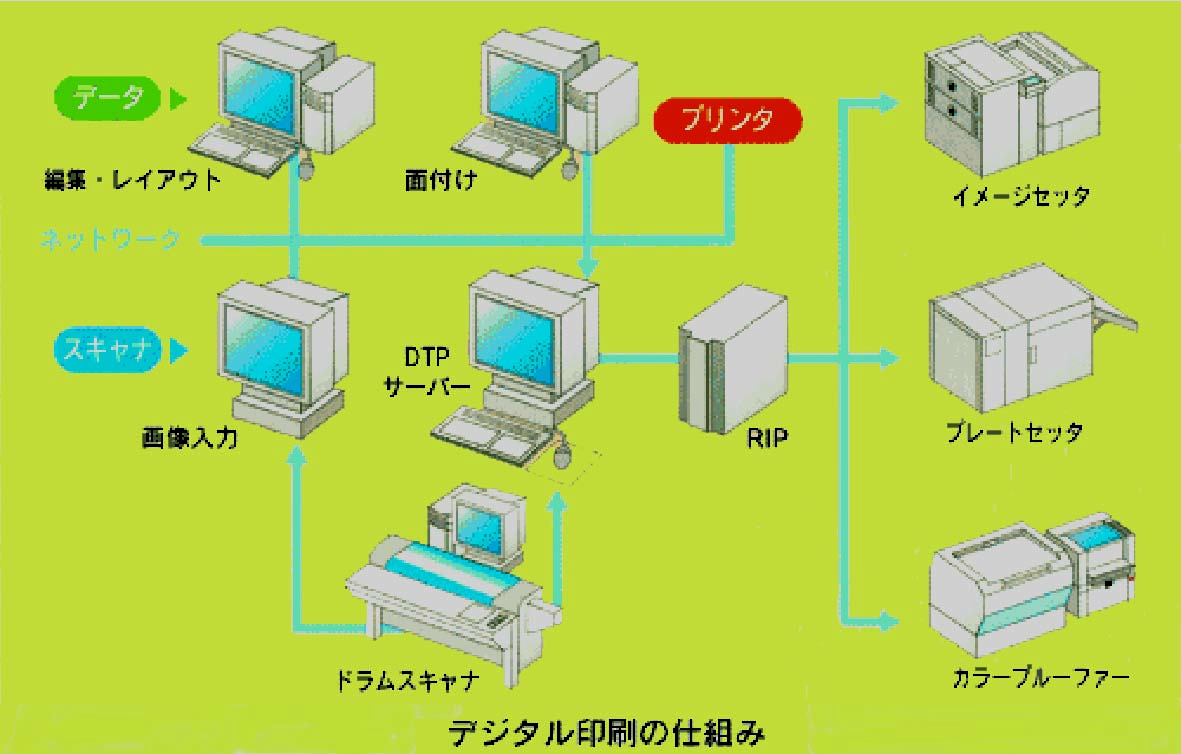校正は、印刷物等の字句や内容、体裁、色彩の誤りや不具合を、あらかじめ修正すること。
ドイツでグーテンベルクが活字を発明して、印刷術の基礎となったことはよく知られていますが、活字や込物(こめもの)で活版を組む作業のことを植字という。
活字だけを集めた(文選)と、句読点,記号,罫線などを段落や行間を整えながら指定された形に組む印刷方式を活版印刷といいます。
誤植や込物が正しく埋め込まれているかをチェックすることを校正といい、そのために数枚印刷する事を校正刷りという。
校正刷りは基本的には2枚で、直(訂正)したものを1枚印刷(製版)部門に届けるというのが一般的な流れであります。
印刷方式が印刷技術の進展により変化をしてきたけれど、印刷は情報の伝達手段ということですから、正しい情報を伝えなくては印刷の役目を果たしません。
活字からコンピューターで文字や画像が作れる時代になったとしても、原稿に忠実に情報が紙面に載っているかどうかは大事な事ですから、そのための校正があります。
いくら文明が進もうとも基本はかわりません。ところが最近は、校正の意味が解かっておらない発注者が多くおります。
校正刷りを出した後、大幅に原稿が変えられることがよくあります。
ヒドイのは原稿の差換えではなくレイアウトまで変わってしまうのですが、印刷業というのは受注生産という受身から、そんな非常識にも抗議ができないと嘆いています。
出版物であっても帳票類でも、印刷に先立って仮刷りを行い、それと原稿の内容を突き合わせ、誤植や体裁上の不備を正すのが校正です。
文字や数字ばかりでなく、デザインや発色の確認も行い、特に発色の確認を行う校正を色校正といいます。
校正は、編集の過程においては、出版すべき原稿をまとめた後、書籍や雑誌などの印刷物の形で商品化する前の最終チェックにあたります。
内職として在宅校正者(ホーム校正)、派遣職員やフリー校正者など業態はさまざまでありますが、専門技術者として出版界では確立された職業です。
校正の手順は、基本的にはまず著者の原稿を植字、もしくはデータ取込して試し刷りした校正刷り(ゲラ刷りとも呼ぶ)の内容を、原稿とつきあわせて確認することから始まる。
校正はあくまでも原稿に忠実に印刷されているかどうか確認することが原則だが、校正者にはその分野に対する専門的な知識が要求されることが多い。
校正作業に際しては、「校正記号」と呼ばれる独特の様式に従って、ゲラ刷りに赤字で注記を書き入れるというのが一般的である。
校正によって判明した誤植は、印刷の原版の修正というかたちで反映され、差し替えられた刷り原稿がさらに校正され、再校・三校と重ねられることもある。
校正を終えることを、「校了」と言う。
このような一連の流れは当然のこととして、公務員などには徹底した教育が必要であろうとおもうのである。
むかしは役場に勤めるのは「頭が良い」、「字がきれい」、「計算が速い」などずば抜けた人が多かったように思うけれど、コンピューターで計算して出力はプリンター、出てきたものを封筒に詰めるだけで、事務職のやらなければならないことが解かっていない。
| | ランクル 2014.3.8-13:52 |
|